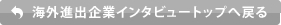多くの企業が抱えるお金の問題について、お話ししたいと思います。
どんなに好不況であっても世の中の企業は2通りに分かれます。
永続する会社と倒産する会社です。
私が思うにこの違いの一つは、財務諸表の企画ができるかで決まります。
財務の観点から考えると多くの会社が永続できないのは、利益に関連する損益計算書に注力しすぎており、お金に直結する貸借対照表を設計するという企画が弱いためです。
なぜなら、企業は赤字でも潰れません。お金が無くなった時に潰れてしまうからです。
では、安全性のある貸借対照表は誰によって、作られるのでしょうか。
どこから資金を調達するのか、稼いだキャッシュを何に使うのか。
これらを決定できるのは、社長だけです。
一方で、収益性の高い損益計算書は、どんなに社長が優秀でも一人では出来ません。
これらは社員が一丸となって作っていくものです。
つまり、お金の管理、つまりBSは社長の責任。利益を作る、つまりPLは社員の責任なのです。
次に利益を作るための予算を立てる際のポイントを考えていきます。
1つ目は、BS から企画する
2つ目は、逆算して考える
1つ目の「BSから企画する」というのは、前述した通り、企業が存続するには、多くのキャッシュを留保することが重要です。
ですが通常、予算を売上から立てるケースが多くあります。
例えば、前年対比10%アップといった、売上を上げることにフォーカスして予算を決めるといったケースです。
あえて言えば、企業にとって重要なのは、売上ではなく、毎月しっかりと利益を出すことです。
利益は、社員を守るためのコストだからです。
また、たとえ売上目標を達成したとしても、思ったより利益が出なかったというのは往々にしてあります。
そのようなドンブリ経営では、会社を存続させて、社員を守っていくことはできません。
そこで予算を作る際には、BSアプローチをとります。
まずは、未来のBSを企画します。1年後・3年後・5年後どのようなBSを作りたいのか。
そして、今期どれだけの内部留保・設備投資・借入金の返済に回していきたいのかという目標を決めます。
今期の内部留保・設備投資・返済の総額が決まると、そこに税率を割り返すことで会社として達成すべき利益額が算出されます。
次に重要なのは、根拠のある目標数字を立てるということです。
利益は社員が作るものですが、根拠がない数字を見ても、社員は動きません。
売上の増加や費用の見直しは、社員一丸となって進めていく必要があります。
では、根拠のある予算を作る為にはどうしたら良いのか。
それが2つ目のポイントである逆算思考です。
先ほどの必達すべき利益から「逆算して考える」ことが大切になります。
必達すべき利益が決まったら、次にすべきことは固変分解です。
固変分解とは、事業活動に発生する費用を大きく2つに分類したものになります。
変動費と固定費の2つです。
変動費は、外注費や原材料など売上の増減に伴って変動する費用を言います。
固定費は、家賃や給料など毎月一定にかかる費用を言います。
この固変分解をしっかり行うことで、直近の数字から実態に沿った企業の収益性を考えていくことが可能になります。
そして、必達すべき利益に昨年の固定費と想定される追加の費用を上乗せすることで、必達すべき粗利益額が出ます。
次に、変動費の額を算出することによって、自社のビジネスモデルにおける粗利益率が想定できます。
そして、必達すべき粗利益額に対して粗利益率を割り返すと、必達すべき売上目標を導き出すことができます。
これで初めて、根拠のある予算の策定が出来ます。
ここから目標とする売上高の達成が実現可能性の検証や戦略の策定へと進み、予算達成が難しいようであれば、変動費や固定費の見直しを行います。
このように、BSを企画し、逆算思考で根拠のある予算策定をすることが、永続する企業になるためには必要になってきます。
また、財務の観点から考えていくにあたって、経営にとって重要なものが2つあることに気付きます。
それは「戦略作りと人づくり」です。
この二軸で考えていきますと、戦略としてまずやるべきは、「社長がB/Sを企画する事」です。
借入金を何年で返済するのか?
理想とする自己資本比率を何年で達成するのか?
それによって必要な利益を逆算し、じゃあ今年はどんな損益構造にしていくのか?
そしてそれに見合う売上目標や販売計画を作ろうという話になっていきます。
それと同時に、他社はどうやっているのかを研究、比較しながら実行していく形になります。
しかし、実際にP/Lを実行していくのは社員ですので、いかに社員との関係性を築いていくか、これが重要になっていきます。
その為にもまず、社長の責任と社員の責任の所在を明確にしておく必要があるわけです。
このように、良い業績を残すにはまずB/Sの企画をし、戦略を練る。
そしてその実行力を高める為の人づくりにも着手する。
この二軸を同時進行で行いながら経営をしていくのです。
弊社では、上記の手法を「月次経営戦略書」というツールを用いて、未来会計という考えのもとに企業の財務分析や予算策定を支援しています。
ご興味がございましたら、サンプルをお持ちしてご覧頂けますので、是非弊社までお問い合わせ下さい。
以上
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支店
大橋 聖也
本記事の執筆者

株式会社東京コンサルティングファーム
大橋 聖也
2012年東京コンサルティンググループ入社。2016年10月にフィリピンに赴任し、現地の日系企業の進出相談、調査、法人設立、会計税務、法務、人事労務案件のサポートに従事。現在、顧客数100社超、日本人5名・フィリピン会計士20名・フィリピン弁護士3名合わせてローカルスタッフ50名超まで事業を拡大中。